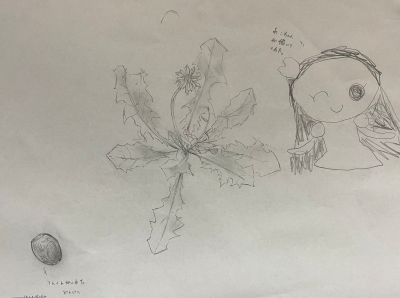10月25日、同法人の桂ぶどうの木こども園の子育て支援事業、出前保育に、2回生片山ゼミの2名の学生がお手伝いで参加しました。
いつもは、浅原公園で開催しているのですが、この日は公園の木の伐採工事があったため、牛ケ瀬公園に行きました。ですが、あまり遊びに来ている子どもがいなかった事から、大般若公園に移動しました。公園の近くまでいくと子どもの声が聞こえました。学生も「子どもの声がする!」とうれしそうに話していました。
ふじ棚のベンチに、テーブルクロスを敷いて、牛乳パックトンボの材料を用紙して、子ども達を誘いました。


やって来た子ども達は、長細く切られた牛乳パックに、油性ペンで模様を描いていきます。自分の好きなアニメのキャラクターの顔やリボンを丁寧に描く子もいれば、家で飼っている犬や、亀を紹介しながら描いてくれる子もいました。乳児さんは、まるをいっぱい描いたり、ジージーとペンを動かすと赤や青、オレンジ、紫と色々な色の線が描ける事を楽しんでいました。



描けた後は、学生のお姉さんにストローをつけて仕上げをしてもらうと完成です。
学生達も完成した牛乳パックトンボをわたす時は、子どもの出来てうれしい気持ちに共感するように「完成したよ」「かわいく出来たね」と声を掛けて手渡していました。
完成した牛乳パックトンボをとばして遊んだ後は、すべり台をする時も、追いかけっこをしている時も、ずっと牛乳パックトンボを持って遊んでくれていました。


今日は、浅原公園が、木の伐採工事だったから、大般若公園でした事を伝えると「今日はラッキーやったわぁ!」と子ども達から嬉しい感想も聞くことが出来ました。